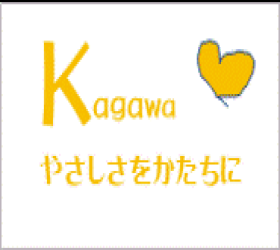障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく千晴訪問介護サービス(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社香川(以下「事業者」という。)が設置する千晴訪問介護サー
ビス(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等が居住する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うもの
とし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 千晴訪問介護サービス
(2)所在地 大阪府堺市北区金岡町2203番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
⑴ 管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
⑵ サービス提供責任者 6名以上(常勤職員 うち1名は管理者兼務)
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア) 利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護である場合にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護である場合にあっては「重度訪問介護計画」、指定同行援護である場合にあっては「同行援護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該計画を交付する。
(イ) 居宅介護計画、重度訪問介護計画又は同行援護計画(以下、「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ) 事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
⑶ 従業者 60名以上(常勤職員 6名以上 非常勤職員 54名以上)
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
⑷ 事務職員 1名以上
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日、
12月30日から1月4日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。
(4)サービス提供時間 午前7時から午後9時までとする。
2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な
体制とする。
3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)にかかわらず、
利用者等からの相談に応じるものとする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児
(4)精神障害者
(5)難病等対象者
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)難病等対象者
3 指定同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)視覚障害を有する身体障害者
(2)視覚障害を有する障害児
(3)難病等対象者
(指定居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食後の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助(事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連携
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(5)同行援護に関する内容
ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆及び代読を含む。)
イ 移動時及び外出先において必要な移動の援護
ウ 排せつ、食事等の介護その他外出の際に必要となる援助
(6) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜として、(2)から(5)までに附帯する、その他必要な介護、家事、相談、助言等
(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合において、提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
3 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、堺市、松原市、東大阪市、大阪市、八尾市、吹田市、大東市の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、及び法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、並びに利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村、大阪府知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、大阪府知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんについては、可能な限り協力するものとする。