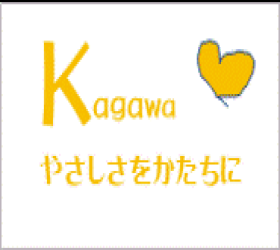障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
千晴デイサービス共生型生活介護運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社香川(以下「事業者」という。)が設置する千晴デイサービス(以下「事 業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の共生型生活介護(以下「指 定生活介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する 事項を定め、指定生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、 排せつ及び食事の介護、創作的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う ものとする。
2 指定生活介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町 村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業 者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下 「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、指定生活介護を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定生活介護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 千晴デイサービス
(2)所在地 大阪府堺市北区百舌鳥綾南町3丁400番地5
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名以上(常勤職員、生活相談員兼務)
管理者は、職員の管理、指定生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状 況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指 定生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行 う。
(2)介護職員
ア 第1単位:1名以上
イ 第2単位:1名以上
介護職員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
(3)看護職員(機能訓練指導員兼務)
ア 第1単位: 1名以上
イ 第2単位: 1名以上
看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上 の指導を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次 のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、8月14日から8月15日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、8月14日から8月15日、12月30日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間
1 単位 午前9時から午後4時15分までとする。
2 単位 午前9時から午後4時15分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は25名(1単位目15名、2単位目10名)とする。
(指定生活介護を提供する主たる対象者)
第7条 事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)第1単位
ア 身体障害者
イ 知的障害者
ウ 精神障害者
エ 難病等対象者
(2)第2単位
ア 身体障害者
イ 知的障害者
ウ 精神障害者
エ 難病等対象者
(指定生活介護の内容)
第8条 事業所で行う指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1)生活介護計画の作成
(2)食事の提供
(3)入浴又は清拭
(4)身体等の介護
(5)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(6)生活相談
(7)健康管理
(8)送迎サービス
(9)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(8)に附帯する離床、着替え及び整容その他 日常生活上必要な介護、支援、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定生活介護を提供した際には、利用者から当該指定生活介護に係る利用者負担 額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から法第29条第3項の 規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指 定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明 書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)次条に規定する通常の実施地域を超えて送迎を行った場合の交通費は片道 500 円 を徴収する。
(2)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
4 前項の費用の徴収に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当 該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費 用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(通常事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、堺市・大阪市・松原市・富田林市・河内長野市・大阪 狭山市とする。
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及 び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、 利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。) の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控 除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第 17 条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、 利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス 等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は指定生活介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意 事項、利用当日の健康状態等を生活介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの 提供を受けるように留意する。
(緊急時等における対応方法)
第13条 現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合 その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」 という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとす る。 2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要 な措置を講ずるものとする。
3 指定生活介護の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サー ビス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報 及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救 出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 提供した指定生活介護に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。) からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する ものとする。
2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48 条第 1 項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の 提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿 書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、大阪府知 事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、大阪府知事及び市町村長か ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとす る。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護 に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うもの とする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者について、職員でなくなった後においても業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するべき旨を、職員に係る雇用契約において規定するものとする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する 際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次 の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的 に実施すること。 (3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(4)苦情解決体制を整備すること。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、成年後見制度の利用支援のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(身体拘束等の禁止)
第18条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体 を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 前項に定めるもののほか、身体拘束等の禁止については、基準省令第35条の2の規定 によるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第20条 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活 介護を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定生活介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相 談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社香川と事業所の管理 者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附 則 この規程は、令和7年2月1日から施行する。